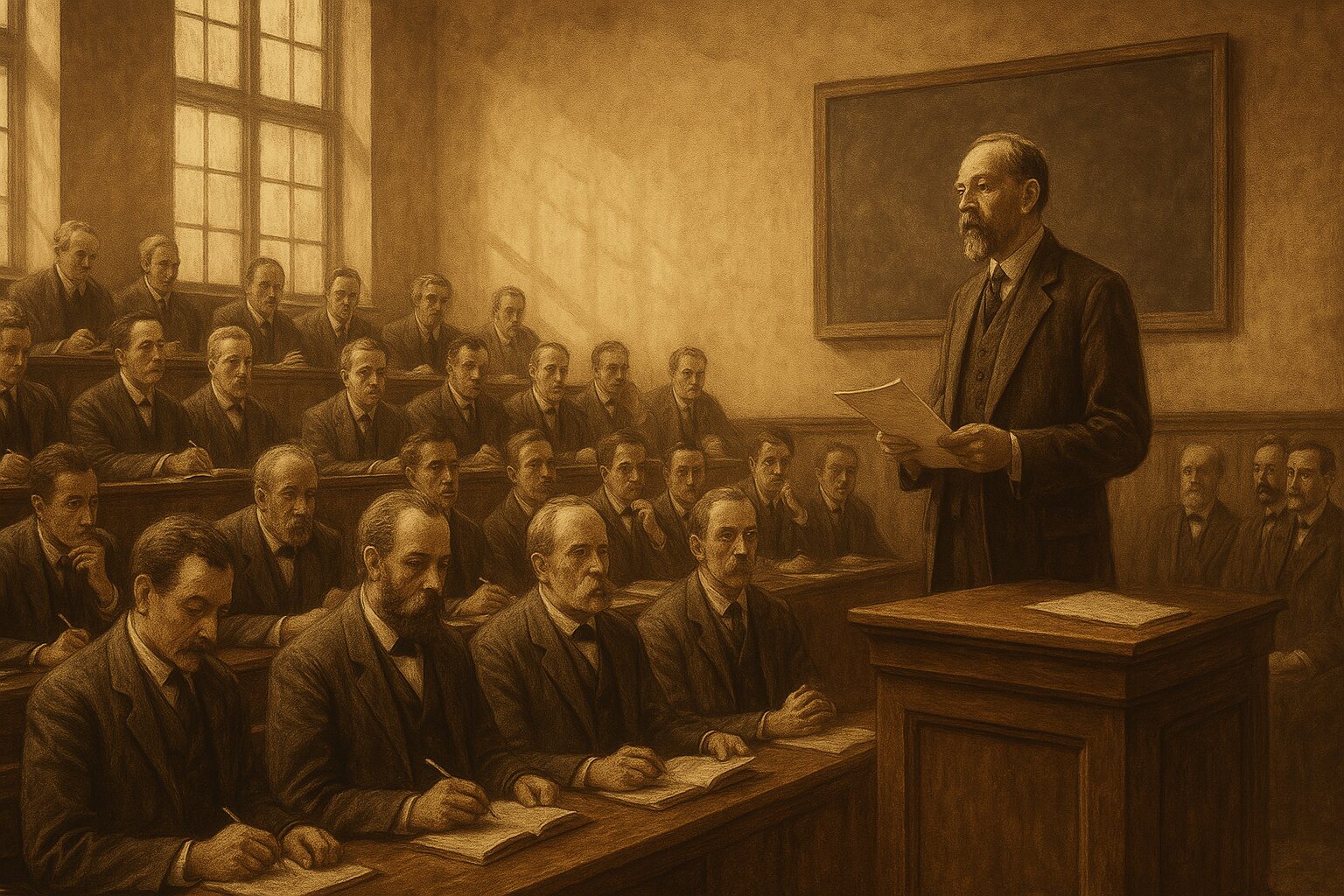人を癒すという概念において、現代多くの人が信仰している科学。
科学は万能でもなければ、実際は再現性という要素が大変重要になってくるため、希少な現象は非科学的であると認定され、調査されずに葬られているというのが現状です。
実際は、希少な現象こそ、再現性を確保するためのアプローチが必要であると筆者は思っています。
科学によって多くの人のQOLが上がりましたし、多くの人の命と健康を救ってきました。
しかし、再現性がないという結果で可能性を潰してしまうのもまた科学であると個人的には認識しています。
そんな流れがはじまったのは、フレスクナー報告書。
この記事では現代の科学信仰を生み出したフレスクナー報告書を解説します。
フレクスナーについて

アブラハム・フレクスナー(1866–1959)。
1910年、米国とカナダの医学教育を調査し*「フレクスナー報告」*をまとめた人物。
医師ではなく教育者であった彼は、当時乱立していた155の医学校を訪問し、その質を厳しく吟味しました。
この報告書は医学教育改革の起爆剤となり、現代医学の方向性を決定づけたと評価されている。
背景と報告書の目的
20世紀初頭、北米の医学教育は統一された基準がなく、玉石混交の状態でした。
医学校の数だけカリキュラムや教育水準が異なり、中には営利目的で低品質な教育を行う学校も存在しました。
こうした状況を是正し医学教育を近代化するため、カーネギー財団の支援のもと、アメリカ医師会(AMA)は教育者のアブラハム・フレクスナーに全国の医学校調査を依頼します。
フレクスナーの任務は、各校の実態を詳細に報告し、医学教育の標準を引き上げる提言を行うことでした。
フレクスナー報告
(正式名称「米国及びカナダにおける医学教育」)は1910年に公表され、その内容は医学教育の抜本的改革を求めるものでした。
報告書はまず医学部への入学条件や卒業認定を厳格化し、十分な基礎教育(解剖学・生理学)と臨床実習を必須とするカリキュラムの導入を提唱しました。
とりわけ強調されたのは、**「主流科学の原則にもとづく教育・研究」**の徹底です。
医学を科学的実験と検証にもとづく学問と位置づけ、大学は研究施設(実験室)を整備し、教授陣も研究者として振る舞うことが理想とされました。
このようにフレクスナー報告は、当時の医学教育に統一基準と科学的厳密さを導入することを目的としていたのです。
医学教育への改革と科学的医療モデルの確立
フレクスナー報告の影響は即座に現れました。
報告書が提示した基準に照らして「不十分」と見なされた多くの医学校が統廃合の対象となり、発表後まもなく北米の医学校の半数近くが合併もしくは閉鎖に追い込まれました。
事実上、報告書は医学部で何が教えられるべきかに枠組みを与え、医学教育の内容に強い影響力を持つことになりました。
これにより医学教育の水準は飛躍的に向上し、米国の医師養成はより実践的かつ科学的なものへと生まれ変わりました。
実験設備を備えた大学病院での臨床研修や、基礎科学の習得を重視した4年制カリキュラムが広く定着したのは、フレクスナー報告の功績といえるでしょう。
同時に、医学教育の焦点は生物学的・科学的アプローチに狭まっていきました。
フレクスナー報告以降、医師は病気の診断と治療を担い、公衆衛生や予防医学は別個の領域とみなされるようになります。
医学校は病気そのものに向き合い、その原因を細胞や微生物レベルで解明しようと努めました。
こうした生物医学モデルの台頭により、身体を生化学的な機械と見なし、薬剤や手術によってその不調を修理するという現代医学の基本観念が形作られました。
このモデルは科学的合理性にもとづく治療法(例えばワクチンや抗生物質)の開発を飛躍的に促進し、多くの疾病克服に貢献しました。
しかし一方で、人間を全体として癒やす伝統的なケアや、病気に伴う苦しみに寄り添う姿勢は影を潜めていきます。
当時、人々は宗教的な癒やしでは病苦が癒えないことに失望しつつあり、科学に希望を見出す風潮が強まっていました。
フレクスナー報告が推し進めた医学の科学化は、まさに時代の要請でもあったと言えますが、その結果、医学におけるスピリチュアルな側面や人間性に根ざした癒やしの要素は長らく軽視されることになったのです。
代替医療・伝統医学への抑圧
フレクスナー報告の最も大きな負の遺産として指摘されるのが、代替医療や伝統医学に対する冷遇です。
当時、いわゆる「正規の医学(=西洋近代医学)」以外にも、オステオパシー医学(整骨療法)やカイロプラクティック、自然療法、ホメオパシー(同種療法)、電気療法、折衷医学(エクレクティック医学)など多種多様な医療流派が一定の支持を得て存在していました。
しかしフレクスナーは、科学的研究にもとづかない医療をことごとく否定し、予防や治療に科学的手段(例えばワクチン接種)を用いない治療体系は「ヤブ医者の治療」や「シャルラタニズム(いかさま医療)」に等しいとまで断じたのです。
報告書の中で彼はこれら非主流の療法を揶揄を込めて「医療のセクト(分派)」と呼び、公的な医療教育から排除すべきだと主張しました。
この報告を受けて、各医学校を管轄する認定機関や出資者は動き出しました。
ホメオパシーや自然療法などを教授していた医学校には、「そうした講座をカリキュラムから外さなければ認定(資格付与)を取り消す」という ultimatum(最後通牒)が突きつけられ、一部の学校は強く抵抗したものの、大勢は報告書の勧告に従わざるを得ませんでした。
結果的に、代替医療系の学校の大半は1910年代に次々と閉鎖され、生き残ったごく少数の学校(主にオステオパシー医学)は西洋医学寄りのカリキュラムへ路線変更していきました。
事実、フレクスナー報告書に名指しされた代替医療学校はほとんどすべてが閉鎖に追い込まれたとされています。
財閥との関係
フレクスナー報告がもたらしたこうした動きには、大財閥の後押しもありました。
石油王ロックフェラーをはじめとする富豪の財団は、西洋医学教育の改革に積極的に資金提供を行い、報告書の勧告に沿ってカリキュラムを近代化した医学部に巨額の寄付金を投じる一方、ホメオパシーやハーブ療法などを教える学校への支援を打ち切りました。
その結果、医科大学で教授される内容は製薬学と手術を中心としたものに統一され、伝統的な植物療法や栄養療法、水治療などは「非科学的」と見なされて主流の教育から姿を消したのです。
こうした歴史的経緯により、北米ではハーブや自然療法といった統合医療的アプローチが軽視される土壌が築かれていきました。
実際、100年以上を経た現在でも、アメリカの医療従事者の中には漢方薬やハーブサプリメントに懐疑的な者が多く、患者がそうした代替療法を口にすると冷ややかな反応を示す、といった文化が根強く残っています。
フレクスナー報告は医学教育の質を飛躍的に高める一方で、人々の医療選択肢を著しく狭めてしまったとも言えます。
欧米において何世紀も受け継がれてきた伝統医学や、各民族固有の自然療法は、20世紀の大半にわたり公式な場から姿を消しました。
その間、それらは「エビデンス(科学的根拠)がない」という理由で一括りにされ、公的な研究資金も配分されにくい状況が続いたのです。
フレクスナー報告書が科学的再現性を重視する医学観を徹底させたことで、生体エネルギー療法や心霊治療など、従来の科学で説明しにくい療法に対しては初めから疑いの目が向けられるようになりました。
この流れは医学のみならず、科学全般における主流の姿勢にも通じています。
未知の現象研究と科学信仰
フレクスナー報告が象徴する「科学的でないもの排除」の姿勢は、医学以外の領域にも影響を与えました。
報告書以降、アカデミズムの世界では「科学的手法で測定・再現できない現象は正当な研究対象とみなさない」という風潮が強まったと指摘できます。
これは言い換えれば、科学への絶対的な信頼(科学信仰)の深化でもありました。
科学だけが真理へ至る唯一の道であるとする考え方は科学主義(サイエンティズム)とも呼ばれますが、それ自体は科学によって実証された命題ではなく、一種の信条だとする見解もあります。
それでも20世紀を通じて多くの研究者や教育者がこの考えを暗黙の前提とし、科学の物差しで捉えられないものは存在しないも同然に扱われる傾向が固定化していきました。
例えば、人智を超えた不思議な現象や心霊現象に対する研究(超心理学など)は、再現性のある証拠をなかなか示せないために主流の学術界から長らく真剣に相手にされませんでした。
実験を行っても同じ結果が繰り返し得られない現象は「科学的でない」と烙印を押され、研究資金も与えられず、公的な学会誌に論文が掲載されることも稀でした。
超能力やテレパシー、気功治療といった未知のテーマは、「証拠が再現できない以上、存在しないも同じ」と見なされてきたのです。
それは裏を返せば、**「再現できれば真実、再現できなければ虚構」という硬直した科学観が支配的になったことを意味します。
この科学観の源流には、フレクスナー報告がもたらした医学教育のパラダイムシフトが少なからず寄与していると考えられます。
医学においてエビデンス(証拠)と再現性が最重視される価値観が確立したことで、それ以外の学問領域にも厳格な科学主義が波及していったからです。
その結果、科学は20世紀に目覚ましい進歩を遂げた一方で、「科学で説明できないものなど存在しない」という極端な世界観が生まれました。
これがいわゆる「現代の科学信仰」であり、人々が科学の威光を絶対視しがちな土壌にはフレクスナー報告以降の教育風土が影響しているとも言えるでしょう。
現代への影響と再評価
100年以上を経た現在、フレクスナー報告が医学にもたらした功罪は改めて見直されています。
医学教育の標準化と科学的手法の導入は、人類にもたらした恩恵が計り知れません。
抗生物質の開発や外科手術の進歩、公衆衛生の向上など、その基盤には科学的訓練を受けた医療人の存在が欠かせず、フレクスナーの功績は今も生きています。
しかし同時に、人々の間では「科学だけでは癒せないものもあるのではないか」という問いが大きくなってきました。
現代医療が発達してもなお、慢性的な病や心の不調に苦しむ人は後を絶たず、西洋医学的な対症療法だけでは十分に対処できない課題が浮かび上がっているからです。
実際、一般市民の間では代替療法や伝統的な癒やしへの関心が再び高まっています。
米国では2000年代に入ってからも大勢の人々が鍼灸やハーブ療法、瞑想やヨガ、気功などを取り入れており、2007年時点で成人の約38%が何らかの代替医療を利用していたとの調査もあります。
1990年代には、代替療法提供者への年間訪問数がプライマリ・ケア(一般診療)医への訪問数を上回ったことさえ報告されています。
こうした傾向は、高度に発達したテクノロジー中心の医療への不満や限界感を反映していると考えられます。
患者はときに画一的な医療システムの中で孤独を感じ、身体だけでなく心や魂をも癒やすケアを求めているのかもしれません。
20世紀末から21世紀にかけて、「スピリチュアリティと医療」の関連性を研究する学問領域や、伝統医療を科学的に検証し統合しようとする試みも進展してきました。
医療者の側でも、ホリスティック医療や統合医療の重要性を見直す動きが見られます。
例えば緩和ケアや心身医療の分野では、西洋医学と伝統的ケアを統合したアプローチが模索されています。
フレクスナー報告書が撒いた種は、科学万能の光と影の両面を持ちました。
私たちはその歴史的背景を静かに見つめ直すことで、現代の医学と科学が抱える課題を深く理解することができます。
科学的知見を尊重しつつも、人間の体験する癒やしや安心といった価値を取り戻すこと――それこそが、フレクスナー報告から1世紀を経た今、改めて問われているテーマではないでしょうか。
科学の力と伝統的知恵を統合し、未知の現象にも開かれた心で向き合う姿勢が、これからの医学と社会に求められているのかもしれません。
参考文献: フレクスナー報告原典navymule9.sakura.ne.jpnavymule9.sakura.ne.jp、関連する医学教育史の研究navymule9.sakura.ne.jp、代替医療の歴史的評価psychologytoday.com、科学哲学的考察knowledge.e.southern.eduなどを参照しました。